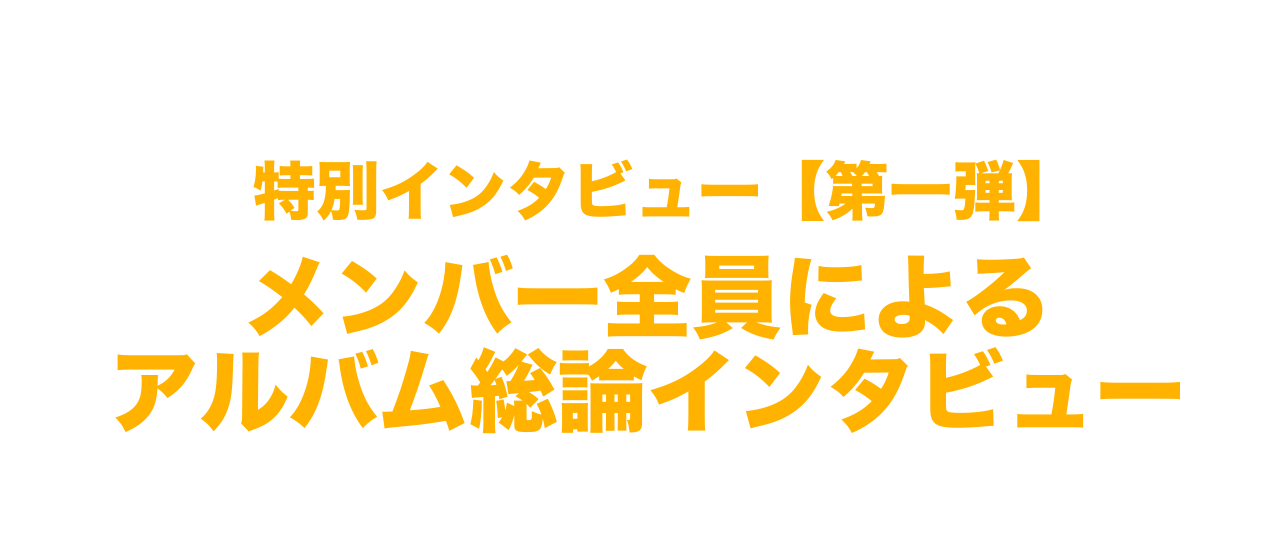
■4年ぶりのアルバムになります。その間にあったこと、そしてとんでもない音楽的飛躍を遂げていること。いろんなポイントがある作品だと思うんですが、まずは『THANK GOD, THERE ARE HUNDREDS OF WAYS TO KiLL ENEMiES』という、非常に物騒なタイトルについて伺っていいですか。
(笑)今までは『SEEDS OF HOPE』とか『PANDORA』とか、覚えやすい言葉を意識してアルバムタイトルをつけてきて。じゃあ逆に、覚えられないようなタイトルをつけても面白いんじゃないかと思って。それで、以前ボツになったTシャツのデザインを思い出して。首を吊っていたり、毒を盛っていたり、いろんな方法で敵を殺しているイラストが載っているデザインだったんですね。そこに書いてあったのが『THANK GOD, THERE ARE HUNDREDS OF WAYS TO KiLL ENEMiES』っていう言葉で。感覚的にこの言葉はいいんじゃないかなと思ってメンバーに聞いてみたら――。
全然いいっしょ!ってね(笑)。
うん、めっちゃええやん!って思った。
■とはいえ作品タイトルというのは作品の象徴でもあるわけですし、少なからず「敵を倒す方法がたくさんある」という言葉に必然性を感じる音が鳴っていたんじゃないかと思うんですけど。そのあたりはどうでしたか。
ああ、そうね。「敵を倒す方法がたくさんあってラッキーだな」っていう意味合いが、SiMの音楽性の幅広さに繋がるなと思ってたんだよね。今までで一番音楽的なバラエティに富んだこの作品を表すタイトルとしてもピッタリだなと思えたし――今回は、本当に頭を使って作ったところが全然ない作品で。出たものをボンボン並べていって、後から考えて曲にしていく作り方をしたんだよね。だからタイトルも、後から意味合いが腑に落ちるっていう感じだったね。
■今のお話は、バンドとしても頭を使うんじゃなく瞬発力だけで音楽を作ろうというモードになっていたということですか。
そうだね。曲や作品を作るにあたって、メンバーそれぞれが「やりたいことだけをやろう」っていう考えで一致したんだよね。逆に言えば、どこかで凝り固まってた自分たちの曲作りとか音選びとかを取っ払おうっていう感じがあった。今回は1曲1曲で音も全然違うし、今までにない音にトライするのは勇気も要ったけど、それも前向きにやれたと思う。
ほんとに、何も考えずに今まで経験してきた素養とか、自分のスタイルが自然な形で解放できた作品ですね。曲を録った時期はそれぞれバラバラだけど、最終的に曲が出揃った時に集大成のような感覚があって。今までに比べても最強の作品ができたなって。
■青写真を先に描くのではなくその都度その都度やりたいことを詰め込めたからこそ、自分の持っているものが自然な形で出せたっていうことですよね。
そうそう。だからこそ、今までになかったアプローチも盛り込めたし。今までのSiM、今までの自分を全部出せたのはもちろん、これからもっと自由になっていけるきっかけの作品にもなった気がするんですよ。
そうだね。曲を作ってるのはMAHくんなので、あくまで彼のやりたいことを全力でサポートする立ち場なのは変わらないんですよ。だけどその上で感じてたのは、1曲1曲が今までになく自由だということで。だからこそ僕もいろんなことができたなって。とはいえ、自分たちが持っているもの以外をやった感覚もなくて――それくらい、自然で本来的なSiMを解放できた作品だなって思いますね。
■SiM史上最も楽曲バラエティに富んでいるし、レゲエもパンクもニューメタルもロカビリーもダブステップもラップミュージックもドラムンベースもガシガシ接続していく点は、これまでで最もカオティックな作風だとも言える。だけどSiMが歌と音で表現してきた人間の混沌という意味で言えば、SiMの本質が最も表れているともとれるし。そこが面白いなと感じて。生きていく上での愛と暴力性と誇りが無濾過で歌われているところも、まさに人間の混沌そのものだなと感じて。
さすがだね(笑)。本当にそうで、今までは曲のアイディアがでた時に、曲を受け取ってくれる人――リスナーやライヴの場にいる人のことをまず考えちゃってて。あるアイディアが出た時に、それをそのまま投げるのがいいのか。キャッチしやすいように柔らかくしてあげるのか。その「受け取られ方」を考えて曲を作ってきたところがあって。でも、それをやめようっていう話し合いをバンドでしたんだよね。思いついたらそのまま投げよう、受け取れるかどうかはお前次第!みたいな。そうすることによって、もっとはっちゃけていて収拾のつかないものになる気もしてたんだけど、結果としてはちゃんと収拾がついてるなって思えてるね。
そこが、1枚目のアルバムとの差だと思う。『Silence iz Mine』の時は聴き手がいるとも想像できずに作ったアルバムだったし、収拾がついてない作品だったなって未だに思うんだけどさ。でも15年やってきて、この4人でやってきた経験が素直な形で出たのが今回のアルバムかな。たとえば転調とか急激な展開も多いけど、それも歪な形というよりは音楽的な面白さにできたと思うし。
■そうですよね。自分たちの快感原則のもとにぎゅっと束になっているのが今回の作品だと思うし、他では聴けない混ざり方と爽快感がある。そこが素晴らしいんですよ。その点で伺うと、聴き手のことを考える以前に自分たちの気持ちいいようにやろうと話し合ったのはなぜだったんですか。
そうだな……自分たちでも薄々感じていた部分が、お客さんにも伝わっちゃってるのかな?って思うことがあってね。具体的に言うと、「どうせSiMはこういう要素を落とし込んでくるよね」っていうことをお客さんが察知するようになっちゃってたし、俺らは俺らでお客さんが喜んでくれるポイントをもうわかっちゃってた。もちろん自分たちのやりたいことをやってきたんだけど、そこに「どう受け取られるか」っていうフィルターが必ず入ってる状態になってた。その「慣れ」みたいなものを取っ払って、ただただ純粋な自分たちを解放しないと、俺たちのそのままの形を見てもらえなくなるんじゃないかって気がしてたんだろうね。
……あのさ、『SAW』っていう映画観たことある?
■ん? はい。
あれ、『1』は「マジか!」ってなったじゃん。
■そうですね、衝撃だった。
で、『2』はまた「おお……!」ってなったよね。
■わかります。
でも『4』にもなると、「どうせ……」って感じだったでしょ。
ははははは! めちゃくちゃわかる。
■免疫がついてしまいますよね(笑)。
そうそう。どんなにショッキングなものでも、人って免疫がつくと構えるようになっちゃうんだよね。そもそも普通のバンドは2番が終わった後にダブステップに行くようなことはしないんだろうけど、でも自然と聴き手は「SiMだから、どうせそうなるんでしょ?」って考えるようになっていく。そこで俺ら自身が窮屈になってたところはあると思うんだよね。
■もちろん、今のお話にはいい面もあるとは思うんですよ。「ラウドロック」っていうラヴェリングとはまったく違う、これだけの音楽的情報量と素養の深さをキャッチーなものにしてきたSiMの音楽にお客さんも調教されてきたところもあるだろうから。ただ、音楽的な深さ以上にSiMっていうバンドのキャラクターのほうが根付いてきた部分もあると思うし、そこで今一度音楽としてSiMを叩きつけることも必要だったのかなと。
本当にそうで、出す曲出す曲「ああ、そういう感じね」って反応されてるだけのような気がしちゃってたんだよね。それが2年くらい前かな? ツアー中のホテルの一室で、珍しくメンバー全員で集まってみんなで話したんだよね。「もう、細かいこと考えるのやめない? 好き勝手やろうよ」って。でもね、その話をするのには勇気も必要だったんだよね。今まで積み上げてきたものを一気に壊すことにもなりかねないから。
■MAHさんからの話を聞いて、それぞれどう思ったんですか。
まあ、俺らって普段からあんまり話し合いとかしないんだけど、ただ、それぞれが沸々と溜まってるものは確実にあったと思うの。「このままでいのかな」って。だからMAHくんが「もう好き勝手にやらない?」って言ってくれた時は「やっぱりそうなんだ!」って思った。これまでのものを壊す怖さや心配よりも、前向きな話ができたなっていう実感があったね。話を切り出してくれて嬉しかったよ。
そうやなあ。確実にみんなが個々で悩んでたと思うんですよ。ここからどうしたらいいのかって。でも、MAHのあのひと言で救われるところがあったんですよね。
やった! 好き勝手できる!って感じだったよね(笑)。
(笑)そういうメンバーの反応に、俺自身も救われたところがあったんですよね。もうリスナーのことを考えることはやめにして、一旦自分のやりたいことだけをやっていいんだなって。解放された気分だったと思う。
■たとえば『THE BEAUTiFUL PEOPLE』までを考えると、海外のヘヴィミュージックを背骨に持つSiMは日本においてオルタナティヴだと自覚してきたからこそ、その音楽を持って規模を拡大していくことを意識していたと思うんです。その姿勢が、日本の音楽全体にとっての起爆剤にも、どうしても保守的なシーンへのステートメントにもなってきた。その結果として横浜アリーナまで駆け上がったけど、それ以降のステップを音楽的に見せていくにはどうしたらいいのか悩んでいたっていうことなんですかね。
そうだね。こういうヘヴィでダークな音楽性、気に食わないことがあるなら何も気にせず吐き出していいっていう精神性も含めて、こういう音楽があるんだよって素直に知ってもらいたかったからね。だからこそ言われた通り、これ以上の規模に行くにはどうしたらいいのか、どういう音楽的な変化を見せればいいのか、悩んでたんだと思う。
実際に俺らが聴いてきたダークでヘヴィなバンドも、世界規模で何百万枚っていうセールスを残してきてたからね。キャラクターの強さや音楽のセンセーショナルさが合致して突き抜けたバンドたちを知ってたからさ。だから俺らも、それを日本でもやれるって信じてたんだよね。
その点で大きかったのは……『PANDORA』のツアーのファイナルで新木場スタジオコースト2日間を売り切ったあたりかな。キャパとしても日本武道館が見えてきて。さっき言った「自分たちも日本で突き抜けられるはずだ」っていう気持ちとは矛盾した話に聞こえるかもしれないけど、「武道館なんて似合わねえだろ。やっぱりライヴハウスでしょ」っていう考えも最初はあったの。でもちょっと待てよと。俺らが聴いてきたヘヴィなバンドたちはもっとデカいところでやってたよなと思って。それに『DEAD POP FESTiVAL』を屋外フェスに拡大するタイミングでもあったし、だとしたら日本武道館もやれるだろうし、もうひとつステップアップできるなって思えたんだよね。だから、ずっとラウドミュージックを押し上げたいっていう気持ちでやってきたというよりも、そのタイミングごとに「よし、今ならここはいけるな」って確認作業を細かくやってきた結果がアリーナクラスでのライヴだったと思うんだよね。
■逆に言うと、逐一「自分たちが大きな場所でやってもいいのか」「このラインまでは大丈夫だけど、ここからはどうか」っていう確認作業をしてきたのは、自分たちの精神性だったり、もっと言えばご自身にとってのロックバンドの美学だったりに照らし合わせていた感覚だったんですか。それはどういう精神性だったんですか。
ロックバンドとは? ロックとは? みたいな精神性の部分を意識していたというよりは、もっと自然に「ロックってこういうもんでしょ」っていう気持ちでやってた感じかな。気に食わないと思うことは叫んでいいし、そもそもダークなものでも暗いことでも吐き出していい音楽だからロックは転がってきたわけじゃん。だってさ、世の中の常識の中では言っちゃいけないことも自由に表現できる音楽がロックのはずでしょ?
■そうですね。社会的な弱者でも、まだ何者にもなれていない人間の心でも、自由に表現できる場所としてロックは生まれた。人の心に対して最も寛容な音楽だし、そもそも自由であったはずですよね。
そうなんだよね。でも、周りを見渡してみたらそういう根本を表現しているバンドが少なかったんだよね。でも俺たちはその根本を忘れてないよっていう気持ちだったし、ロックバンドの精神性を背負うというよりも、元々こういうものでしょっていう自然な態度だったと思うの。だからこそライヴの熱量や生々しさっていう部分が大事だったし、ライヴハウスのバンドである自覚はそこからきてたと思うんだけど。もちろん日本のお国柄もあって、普通の人が普通のことを歌うバンドのスタイルが根付いてきたのかもしれないけどね? でも俺はそうじゃなくて、もっと刺々しいことも、普段は言っちゃいけないとされてることも歌えるのがロックバンドだと思ってきたから。
■そうですよね。
それにさ、日本武道館とか横浜アリーナまでやったからこそ、日本にはまだまだSiMを知らない人たちがたくさんいるんだなって実感することも多かったんですよ。で、意外と俺たちはそういう時に土足で踏み荒らしていくバンドではないわけですよ(笑)。
■はい(笑)。リスナーを音楽とライヴに巻き込むことに対して、とても丁寧なパフォーマンスをしてきたバンドですよね。
そう。「初めて来た人なんですね、じゃあこうやってみようか」っていうふうにやってきたつもりなんです。それがデカかったと思うのね。丁寧にお客さんのことを考えてきた結果として、フェスに出ても大体の人がSiMを知ってたり、観たことがなくてもSiMのイメージが根付いていたりするようになった。それを実感できてから、だんだんと「受け止めやすいものを作ろう」っていう意識はもう必要ないと思えるようになったのかな。
■そこから“LET iT END”、“DiAMOND”、“LiON’S DEN”といった配信シングルを立て続けにリリースされていきましたが、実際に自分から出てくる音楽はどう変化していったと思いますか。
たとえば『龍の如く 極2』のテーマソングとして“A”を出したけど、その時はまだ迷いがあったと思う。自分たちのやりたいことと、お客さんが楽しめるものとの間で。だけどその後にバンド4人で話したから一気に吹っ切れて。“DiAMOND”や“LiON’S DEN”ではどちらも5弦ベース、7弦ギターを使うようになったのね。
■より落としたチューニングが可能になったと。
そう。それによって、日本のシーンではなかなか聴けないヘヴィネスを表現できるようになった。しかもどちらもタイアップ曲なのに、いきなりドゥーン!っていう重低音から始まる。そういうイタズラ心というか、「こんなの聴いたことないっしょ?」って提示して面白がるようなところが解放されていった気はする。こんなの聴いたことないと思うけど、でも俺らはヘヴィなのが好きなんだよねって。好きなものをそのままやろうっていうモードを、あの配信シングルの頃から布石として表現できてたんだと思う。
■純粋に伺いたいんですけど、ここまでヘヴィな音楽性でやってきたバンドが、ヘヴィネスの部分でリミッターをかけていたのはなぜだったんですか。
それはね、(極端にヘヴィな音を)元々やってたからだと思う(笑)。
そうそう、俺とMAHくんがSiMの初期まで並行してやってた「JANE Doe」っていうバンドでは、5弦ベースと7弦ギターを使ってたの。それで満足してたところもあったし、純粋にここまでヘヴィだと広がらないんだなってことも実感してたし。それもあって、SiMでも最初はドロップD(チューニングの名称)でやってたんだけど。でもそこから何周かして、10代初期に聴いていたヘヴィな音楽に回帰したら、今はまた新しいものになるんじゃない?っていう予感も生まれてきて。
■たとえば“BULLY”も、ドスンとチューニングを落としたギターが印象的なんですね。だけどその分サビのキャッチーさや、ラップが引っ張るヴァースの心地よさが吟味されていて。そのあたりのバランス感覚が一貫して素晴らしいですよね。
5弦ベース、7弦ギターになると、今度は歌もめちゃくちゃダークでドロッとしたほうに持っていきたくもなるんですよ。たとえばKORNみたいなね。実際のサウンドがヘヴィなわけだから、感情や歌としても内側が引っ張られそうになる。ただ曲を作っている途中で、サウンドがどんなにダークでも、今まで通りのSiMのヴォーカルラインが乗せられるなって思えて。サウンドがよりヘヴィになったからこういう歌い方にしようとかじゃなくて、ただサウンドで新しい武器を手に入れただけだから。だから結局残った曲たちを聴いてみると、人によっては5弦ベースや7弦ギターを使っていると気づかないくらい爽快感のあるメロディだったりヴォーカルだったりになってると思う。だけど、実際にバンドとして表現できる楽曲の幅は格段に上がったっていう。
確かに。俺もそんなにチューニング下げてるって感じせえへんもん。
いや、GODRiが気づかないのはヤバいでしょ(笑)。
■ははははは。
ドロップDだけじゃなくて、ドロップCもやり尽くした感はあったからね。たとえば俺らのサビによくあったのが、8フレットを押さえて、その次に開放っていうコード進行(G#→C)だったんですよ。それも、チューニングがドロップGになるだけで全然違うものに聴こえてくるんだよね(D#→G)。俺のメロディが飛んでるところは変わらないんだけど、チューニングを下げたことによってサウンドとの幅が出てくる。その分、飛翔感とか爽快感がより強烈に感じられるようになったというか。
■なるほど。その点で言うと、『THE BEAUTiFUL PEOPLE』までにMAHさんのテーマのひとつになっていたのが歌のスキルアップでしたよね。メロディの滑らかさやポップネスを磨いてきたことがより一層武器になってきたとも言えるのかなと。
確かに。だからか、サウンドがどれだけ好き放題やっていてもサビで一気に景色が変わるというか。そういう曲は多いかもしれないね。ラップが増えているのも含めて、自分の歌の幅自体も広げられるようになった。それはやっぱりサウンド面で新しい武器――よりヘヴィネスを解放できたことが大きかったんだと思う。
■ラップのお話も出ましたが、たとえば『i AGAiNST i』も、状況が大きくなったタイミングでレゲエの要素やラップを増やして、自分たちのルーツの深さを見せようという実験的な部分がありましたよね。ただ、今回はリスナーに対する実験すら飛び超えているし、歌われているメッセージとしても、サウンドのヘヴィネスと合致するようにして、より直接的に人生の在り方や気に食わないものに言及していると思ったんですよ。MAHさんという人間の本来的な混沌も、人生観も、全部歌い尽くそうという執念が半端じゃないというか。
ああ……確かに人生全部が出てるっていうのはそうかも。これは同世代のバンドもそうだと思うんだけど、歌詞の部分に関しても、歌い尽くしてきた感があった。怒りについての曲もたくさん出してきたし、悲しみの歌も何十と出してきた。じゃあ今の自分が歌いたいことってなんだろう?って考えていくとさ、特に何も考えずに過ごしてる1日もあるわけじゃない? そこで考えて捻り出して歌詞を書くのは、俺のジャッジとしては嘘になるの。素直に出てきたものじゃないからね。今ムカついてないんだったら怒りの歌は書けないし、今悲しくないんだったら悲しみの歌は書けない。じゃあ今の自分が歌にしたいことはなんだって考えていったら――たとえば去年俺が一番やってたゲームはNBAバスケのゲームだったんだけど、歌詞にバスケの用語をガンガン入れてみようと思ったりして(笑)。そのほうが俺のリアルだなって思えたんだよね。でも曲ごとに、リアルな俺の怒りから出てきたものもあるし。そういう意味で、より俺っていう人間の人生がそのまま出てる感じはあるかもね。
■言い換えてみると、SiMのMAHとして歌いたいことというよりも、ひとりの人間としてのリアルな感情だったり、生活に近いところから生まれる喜怒哀楽だったりを歌にできるようになったということですか。
そういうことなのかもしれないね。ラストに入ってる“FATHERS”なんかはまさに、結婚して子供が生まれてからの「父親としての生活」によって生まれてきたものだと思うし。やっぱり今までは、SiMのMAHっていう悪魔的なキャラクターを間口にしてきたところもあって。だけど好き放題やろうと吹っ切れたことで、そんなキャラクター性を守ることすらも関係ないと思えたんだろうね。本名の俺も、SiMのMAHも、乖離はしているけど同じ俺なんだよなって。自分の中の別人格に対しても開き直れたのは大きかったんだと思う。
■前作までの流れも承知した上で敢えて聞きますが、どうして自分の中の乖離に対して開き直れたんだと思いますか。
やっぱり『THE BEAUTiFUL PEOPLE』で自分の中の孤独とか内省を吐き出し切れたのが大きかったんだろうね。SiMのMAHっていうキャラクターがひとり歩きすればするほど、本来の自分とは違う存在が大きくなっていって。その歪みみたいな部分を吐き出して、「誰も知らないだろうけど、こんな俺もいるんだよ」っていうことを歌えたから。それに、やっぱり結婚を公表して家庭を持ったことも自分にとって大きかったと思う。どれだけ激しいライヴをしても、家に帰れば家族がいて、SiMのMAHっていう存在はそこで自然とリセットされるわけですよ。そうなると、MAHはMAHでどこまでも振り切れればいいと思えるようになったし、普段の生活をしている自分自身も間違いなく俺であるっていう感覚が生まれてきたんだよね。……そういう変化は歌に出てるんだと思う。
■なるほど。そのあたりは、各曲の話とMAHさんのソロインタヴューでもでさらに深く伺っていければと思います。では、各曲からより深く今作を紐解いていく全曲解説インタヴューに行きましょうか。
ふう、まだまだ長丁場だね(笑)。
■お付き合いのほど、よろしくお願いします。
うっす、よろしくお願いします!
interviewed by Daichi Yajima
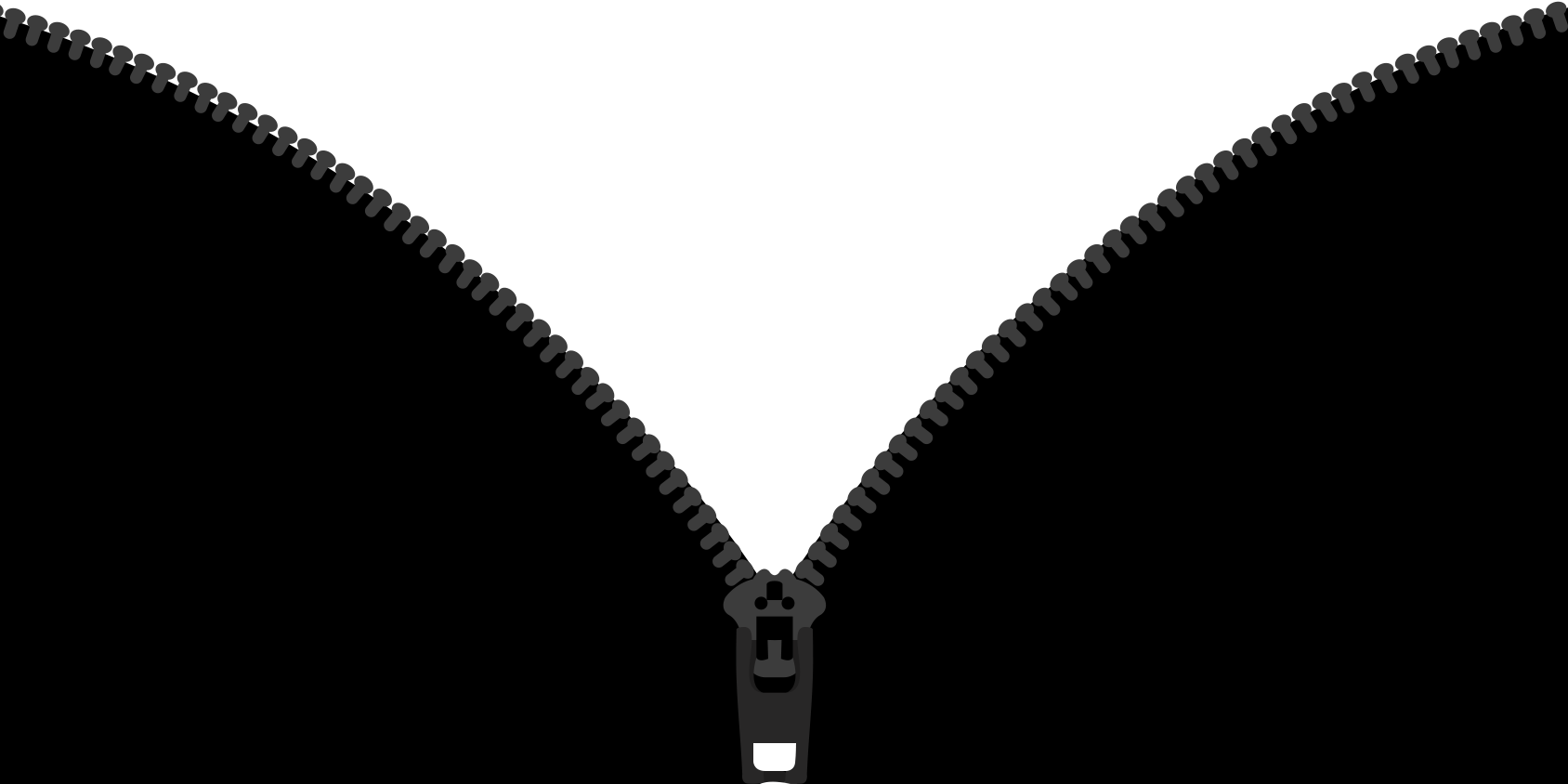
JavaScriptが無効化されています。
JavaScriptスクリプトを有効にしてください